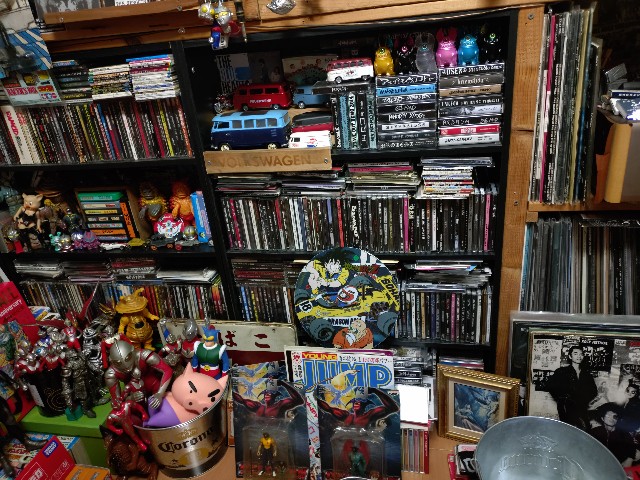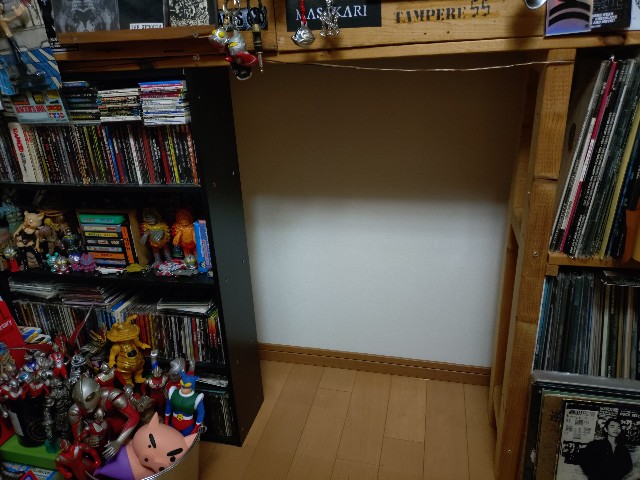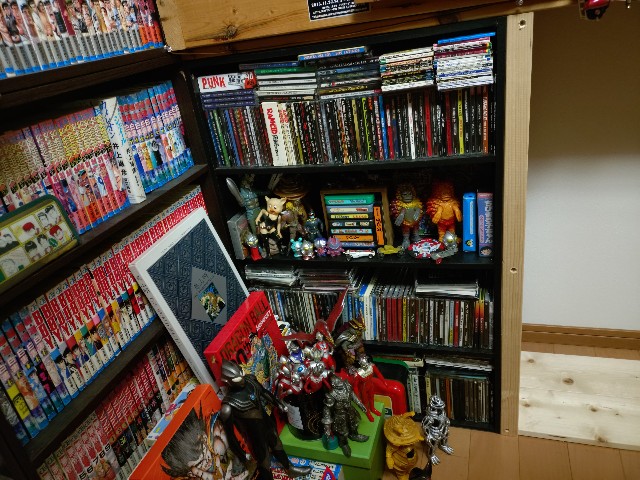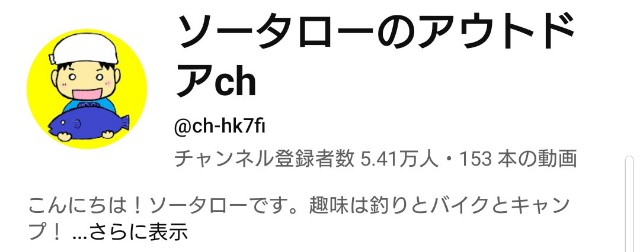「はりま風土記の里を歩く」
の、

「伊和大神を袖にした安志比売の里を歩く」
を、歩いてみました。
と言っても移動は車です()
今日は仕事が安富の小学校だったので、そう言えば行った事なかったな〜、と思い出したのが「安志加茂神社」
加茂神社の拝殿天井に不動孝雄氏の絵が奉納されていて、見たかったのと併せて諸々行こうで上の本です。

先ずは石作神社に。
左は願寿寺でこちらの奥が石作神社。

この鳥居横に、

石碑があり、「牛頭天王」の名が彫られていました。
石作神社は何の予備知識も無しに行くがスサノオ関係なんかな?とワクワク。


石作神社に到着、参拝。

祭神に「素蓋鳴命」とあり、やっぱしと。
他の神々は猿田彦大神、火産亚神、菅原道真命、若年神、大年神、御年神、火具土神が祀られていて複雑です()
宮司変われば、と言った感じで。

大八車かな?

神武天皇。

右はバリバリ近代ですね()

手水舎。
蛇口は無し。

石階段中腹から寺が見える。
ここを右に行くと、

高取山登山口があった。
宍粟50名山に数えられる山やがまだ行った事ないので、また暇を見て登りに行こう。
お寺にも。


めっちゃ立派。

鐘も立派。

これか〜。
と言うのも、

「はりま風土記の里を歩く」に記載されていたのです。
親鸞聖人像。
(聖地巡礼みたいですね 笑)
次の聖地に。

こちらは「篳篥神社」、ヒチリキと読む。

この神社は伊和神社の遥拝所である、神功皇后が三韓征伐のとき伊和神社に参拝するためこの地まで行啓されたが、ここより奥は道がけわしく、通行困難の為ここで遙拝された
また延久年間(一〇六九)から毎年六月十五日に宮中の楽人か伊和神社で管弦を奏していた。たまたま、後三條院の時洪水となり交通が絶えたので、この社で奏楽することにしたが「ひちりき」のお
この続きの写真(石碑の横)を撮っていませんでした 笑。
この石碑にも刻まれる神功皇后の三韓征伐ですが、神功皇后は本当に三韓征伐をしたんやろうか?と言う疑問がある。
古代朝鮮の王であったアメノヒボコ(天日槍)、の末裔とされている神功皇后が何故三韓征伐をする必要があったんやろう?と。
御先祖様の国を征伐しに行くかね?と 笑。
神功皇后とは別に上皇様が
「桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると、『続日本紀』に記されていることに、韓国とのゆかりを感じています」
と仰っていました。(こちらは映像も見た事ある)
記事↓

https://share.google/0en72qDrCFmXU9TAA
古代朝鮮との縁は多々あるのでしょう。
(スサノオも朝鮮半島から来た渡来人と言う説もある)
※言うまでもないが、これは古代の話です
話がそれたので戻すと、

拝殿。
ここからは本には記載されていないが、

聖山城址に。

道がしっかりあるので楽に登れます。

愛宕神社。

眺望良し。
城趾はまだ少しだけ上です。

程なく到着。

こちらも眺望良し。

説明書き。
聖山城址
出石地区を流れる揖保川左岸の標高約一六八材の尾根上に築かれた山城で、明応二年(一四九三) 宇野氏の重臣下村氏によって築城されたと伝わる
その後云々と書かれ、羽柴秀吉(豊臣)によって落城されたと。
秀吉くんはほんまに播磨の城をどんだけ落としたら気が済むんや()
ちなみに↓

中世播磨250の山城にも記載されています。

それから下山し、本にも記載される、
安志加茂神社に。

拝殿。

拝殿天井画 作 不動貴雄
「別雷神龍遣降臨図」
を、ようやく見れました。
物凄いので是非とも。


土俵があり、ここでは相撲が奉納されるそうな。


弁天さんに続く橋。

弁天さん奥の院。
また移動し、

こちらも本にも記載されているし、伊和大神ファンとして行きたかった「安志姫神社」
播磨国風土記には、伊和の大神が安師比売神に求婚したが拒絶され、怒った大神が、川上を石でせきとめて、三方の里(一宮町三方)の方へ流したので水の少ない川になった。この川は、神の名を採って安師川といい、これまで酒加の里、後に山守の里といったのを川の名によって安師の里と改名したと述べている。
兵庫県神社誌より引用。
このエピソードが好きで来たかったのです 笑。
ま、実際は解らんけどね 笑。

参道の石階段。
石積も良し。

到着。
加茂神社とは違って人の手が行き届いてはいなかったものの良い雰囲気でした。
この後は少し休憩がてら、

ゆず工房にてソフトクリームを。
おいしゅうございました。
次もまた本に記載される地、

塩野古墳に。
ここは国道29号線から見えていて、ここもまた来たかったところ。

六角古墳。(六角墳の発見としては日本初らしい)
中を見ると巨岩がチラホラ見える。
ここも山で、中腹までには全然届かないがそこそこ登るところにあって、こんな岩をどうやって運んだんやろう?と不思議で仕方ない。
昔の人は恐ろしいな、と。
あと1番謎なのが、
「須恵器の年代観から、古墳の築造時期は古墳時代終末の7世紀後半と考えられる。」
とあるが、疑問なのが被葬者は不明との事で。

播磨国風土記の成立が715年で8世紀初頭。
塩野六角古墳の築造が690年やとしても20数年前の事が播磨国風土記に書かれんものかね、と。
う〜む。。。
ちなみにwikipediaには↓
「被葬者は明らかでないが、林田川沿いの平野部を治めた人物の墓と推測され、特に播磨国風土記・平城宮跡出土木簡から山部氏と想定する説が挙げられている」
とあり、なんとなく現実味はあるがあくまでもこれは現代人による推測、想定に過ぎません。
続けて多角形墳について↓
多角形墳は道教・仏教思想に由来するといわれ、特に古代の天皇陵にも採用された八角墳が多く知られる[2]。それに対して六角墳は本古墳が全国で初めての確認例であり、現在ではほかにマルコ山古墳(奈良県高市郡明日香村)・奥池3号墳(岡山県岡山市)のみで確認されているとする説があるが[2]、真崎1号墳(茨城県東海村)や杉山A号墳(長野県千曲市)も六角墳とされる。
道教仏教思想由来と言う見方は面白いですね。
六角墳は結構珍しいと言えるのに、各地バラけてあるのも面白いし。
(播磨は古墳が多いからしっかり調査すればまだまだあるかもしれんが)

古墳裏に獣避けのゲート。

登れそうですが今日はもう下山。

眺望も少し。
これにて今回は終了。
「はりま風土記の里を歩く」ですが、結構楽しめる事が解りました 笑。
ただ記載の同じルートを歩くにはそこそこな時間を要する事も解ったので、歩くなら仕事後ではなく休日、それも朝からじゃないと忙しいかもしれません。
忙しいのが嫌なら今回みたいに移動は車で。
いやしかし良き旅でした。